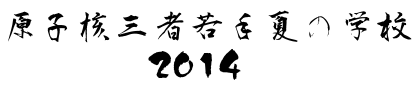開催期間: 2014年8月4日(月)~2014年8月9日(土)
登録期間: 2014年6月23日(月)~2014年7月11日(金)
開催地: パノラマランド木島平
〒389-2303 長野県下高井郡木島平村大字上木島3878-2

協賛: 日本物理学会, 理研仁科センター, 核物理研究センター(RCNP), 高エネルギー物理学研究者会議
講義スライドの公開は講師の方のご厚意によるものです。個人的な学習のために使用してください。講義で使用されていた図や写真等は諸事情により省略されている場合があります。
三者共通講義
格子QCD入門
青木慎也 氏(京都大学)
まず、イントロとして、格子QCDで現在どのような研究が行われているかを紹介する。そこでは、ハドロン質量の計算、行列要素の計算、有限温度相転移の研究、ハドロン間相互作用の研究などの題材について、最新の結果を交えて紹介する。それに引き続いて、格子QCDの基礎となる格子理論を解説する。そこでは、格子状のゲージ場、格子フェルミオンの問題点とその解決法、格子QCDの数値計算の基礎などを講義する予定である。
スライド
素粒子パート(場の理論、現象論、弦理論)
場の理論: 場の理論の位相的ソリトンとその役割
衛藤稔 氏(山形大学)
本講義では、場の理論において位相的ソリトンが果たす役割について様々な角度から解説します。位相的ソリトンに関する基礎的な内容から始めて、インスタントン、モノポール、渦解の構成法とそのモジュライ空間について、またゲージ理論の非摂動的効果との関係、さらに高密度QCDにおけるカラー超伝導渦やモノポールに関して、最近の研究にも触れながら位相的ソリトンの多面的な性質について紹介します。
スライド
現象論: レプトンフレーバー
佐藤丈 氏(埼玉大学)
強い相互作用をしない素粒子はレプトンと呼ばれている。荷電レプトンと電荷を持たないニュートリノがそれぞれ三種類存在していてペアを組み、電子、ミュー、タウの各フレーバーを保存する量子数として持っている。素粒子標準理論ではこれらは厳密に保存するが、ニュートリノに関しては保存しないことが確定し、標準理論の拡張が必要となっている。この講義ではレプトンフレーバーがどういった保存量であるかについて説明し、ニュートリノ振動現象における破れからどのように拡張されるべきか、その帰結として荷電レプトンのフレーバーの破れにどのような影響が出うるか、などについて紹介していく。
スライド1
スライド2
スライド3
弦理論: 弦理論とは何だろうか
米谷民明 氏(放送大学)
弦理論は1960年代終盤から1970年代の前半にかけて生み出され、1980年代中盤から、重力を含む力と物質の統一理論として発展してきた。この講義では弦理論のこれまでの発展の歴史を振り返りつつ、弦理論の位置付けと考え方の基礎、展望を初学者向きに解説する。
さらに、1990年代中盤から現在まで弦理論の潮流の中でも最も重要な役割を果たしてきたゲージ/重力対応(CFT/AdS対応)の基礎を具体例で論じ、今後の弦理論の課題について考える。
スライド
原子核パート
強い場の物理とそのハドロン物理への応用
板倉数記 氏(高エネルギー加速器研究機構)
地球上で人類が創り出せる定常的磁場の最高強度を十数桁も凌ぐ激烈な場が、自然界、特にハドロン物理が関係する現象や過程で生成しており、その影響を真剣に検討することの重要性が最近になって徐々に認識されつつある。具体的には、中性子星やマグネターといったコンパクトな天体は超強力な磁場を持ち、それに起因すると考えられる現象が幾つも存在する。ハドロン物理には、強い磁場が存在するもとでの核物質やクォーク物質の静的、あるいは動的な性質の変化を理解することが要求されている。また、高エネルギーハドロン散乱、重イオン衝突においては衝突時に超強力な電磁場と共に超強力な「カラー電磁場(グルーオン場」も生成する。その強いカラー電磁場の時間発展を理解することは、クォーク・グルーオンプラズマの生成過程を理解することに他ならず、非常に重要な問題であることは理解されるだろう。一方で、最近のレーザー強度の発展はめざましく、高強度レーザーを用いて、強い場が存在するときに起こる新しい現象をつぶさに観察することができる時期が間近に迫っている。
本講演ではまず、そのような強い電磁場中で起こる特徴的な現象を扱う「強い場の物理」についての基本的な考え方を説明した後、様々な現象を記述する場の量子論的な手法を導入する。それらを用いて、具体的に扱う問題として、強い電場中で生ずる粒子対生成である「Schwinger機構」や、強い磁場中における光子が示す複屈折現象、ハドロンの性質変化を詳しく解説する。また、それらの結果が示唆する中性子星、マグネター、重イオン衝突における特徴的な現象にも言及する。
スライド1
スライド2
スライド3
スライド4
中間子-原子核系で探る核内中間子の性質と強い相互作用の対称性
比連崎悟 氏(奈良女子大学)
強い相互作用の持つ対称性の破れのパターンから現実世界のハドロンの性質を理解しようとする試みは長い歴史があって、カイラル対称性の自発的破れ、UA(1)量子異常、有限のクォーク質量等から、中間子の質量スペクトルを始めとするハドロンの性質が理解されてきています。また、これと関連して、原子核中におけるハドロンの性質の変化を通じて、強い相互作用の持つ対称性の破れと回復に関する知見を得ることを目指した試みも活発に行われています。ここでは、中間子-原子核系の束縛エネルギー・崩壊幅や、核内での中間子崩壊により生成された粒子対の不変質量分布、中間子の核内透過確立などの観測量から、強い相互作用の情報を引き出す最近の研究を概観したいと考えています。
スライド1
スライド2
連続状態離散化チャネル結合法の発展と応用
松本琢磨 氏(九州大学)
原子核物理の研究分野において不安定核の構造研究が重要なテーマの一つである。この不安定核構造の探索は不安定核ビームを用いた実験によって行われており、その実験データから精密に構造の情報を引き出すには、信頼性のある反応理論解析が必要とされる。その一つの有用な解析方法として連続状態離散化チャネル結合法(CDCC法)があり、講義ではこのCDCC法の要点を、これまでの解析結果を紹介しながら分かりやすく解説する予定である。
スライド
原子核のスピン・アイソスピン対称性をどうみるか?(レビュートーク)
笹野匡紀 氏 (理研)
スライド
中性子星で探る核物質の状態方程式(レビュートーク)
中里健一郎 氏 (東京理科大)
スライド
高エネルギーパート
LHCが切り拓くテラスケール物理:新粒子探索の現状と展望
寺師弘二 氏(東京大学)
2012年のCERN・LHCでの新粒子発見以来、素粒子物理の実験・理論研究は新たな局面に入ってきた。発見された粒子の性質測定から、その粒子は素粒子標準模型で期待されるヒッグス粒子である確率が高まっている。その一方、標準模型を超える新しい物理の兆候は未だLHCでは見付かっていない。新しい物理の筆頭候補である超対称性理論や、余剰次元、新しい強い相互作用の模型などから示唆される新粒子の実験探索は、"標準模型ヒッグス"を説明できるシナリオを元に再構築され始めている。LHCでの新粒子探索の現状と将来の展望を、余剰次元などのExoticな物理を中心に解説する。
スライド
高エネルギーニュートリノ天文学の幕開け
間瀬圭一 氏(千葉大学)
IceCubeは南極氷河を用いて深宇宙から飛来する高エネルギーニュートリノを観測するユニークな検出器である。検出器完成後の観測により、PeVという非常にエネルギーの高い2つのニュートリノ候補事象を捕えた。その後のフォローアップ解析により、より低エネルギーのニュートリノ候補事象を更に26事象観測し、高エネルギーのニュートリノが銀河系外から来ている証拠を得た。この講義ではこれらのIceCube実験の最新結果を示すと共に、それがもたらす知見について述べる。
スライド